« パックマンが | メイン | USBメモリにMS-DOS起動ディスクを作成する方法 »
2010年06月14日
GeForce GTX 285を低電圧駆動化・ファン回転数を調整する方法(BIOS書き換え)

お待たせ?しました。BIOSの変更方法、今回はNVIDIA編。対象カードは玄人志向さんの「GF-GTX285-E1GHW/HDG」、GALAXYさんの「GALAXY GF PGTX285/1024D3/GE」です。
前回のRADEONの低電圧動作記事から間が開いていますが、あの話題はかなりのアクセス数を出しているみたいで、割と認知されているものらしいです(汗)。ネタで書いたこともあり、文章が変ですみません。一部修正してあります。しかしながら、同じような境遇にあっている方がそれだけいるという証でしょうか。
末尾に記載した意見が、いきなり5800系に生かされていたのでびっくりでしたけど・・・逆に、指摘するポイントは間違っていなかったともいえるのでしょうか。それはさておいて。
今回は上記2カード、GeForce GTX 285でのBIOSチューニング法です。ATIさんに比べるとスマートに仕上げられるのがポイントでしょうか。こちらも多数の会社でカードを出されているため、すべてを調べ上げるのは困難です。
しかしながら各社のBIOSが一堂に集められているTECHPOWERUPさんを覗くことができれば、おおよその傾向はつかめるというもの。そう、オーバークロックカード以外はほぼNVIDIA社のリファレンスパラメーターをそのまま利用しているのですね。
それらを踏まえて、今回矛先に上がった2枚のカード・・・それは、オリジナルファン搭載製品ということで、いじり甲斐があるというもの。スクリーンショットを踏まえてご案内です。
発売から1年以上経過した今でも、なお定評のあるGTX 285。それは消費電力とパフォーマンスのバランスが、今回発表されたGTX 480/470と比べても見劣りするものではないからですね。昔はATI社よりも効率は上といわれてきましたが、昨年の今頃発表されたEvergreen・・・RADEON HD 5870/5850の後塵を拝する事態に。
いえ、別に480/470が悪いわけではなく、ビッグチップであることと高めの電圧をかけないと動かない模様なので、その分で電力増は避けられないのでしょうし、記事をいろいろと読んでいると・・・
DirectX 11においては文句なしのパフォーマンスを発揮しており、新しく追加されたテッセレーションのステージはEvergreenを寄せ付けないほど。その効率があまりにもよすぎて、常にフル稼働状態となり電力消費がMAX近辺に張り付いてしまう・・・らしいです。
いずれにしてもTSMCでの量産効果がまだ現れていないためコストが高いままとなってしまい、普及にはほど遠い状況ですよね。今後は改善するのでしょうが、その頃には28nm世代へと移行するでしょうから、きりがないものです。
ゆえ、480/470は先取りしすぎた感が拭えず、今ようやくDX10タイトルが増えてきたさなか、昔のDX9の両方を効率よく動かせられるGTX285/275は未だに注目される存在です。私が狙うのは・・・そう、今度はNVIDIAさんが やればできる子 へ変わってもらおうというわけです(汗笑)。
Evergreenの電力効率はすばらしいものがあり、アイドル時で27W、高負荷時でも180W以内という良好な値を出しており、NVIDIAさんが置いてきぼりを食らった格好です。
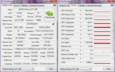 しかし、こちらも回路自体はいいものを積んでいるため、いろいろと調べていきますと・・・おお~、すばらしいじゃないですか、これは('-'*) どのくらいすばらしいかは、こちらのスクリーンショットをみていただければ一目瞭然でしょう。
しかし、こちらも回路自体はいいものを積んでいるため、いろいろと調べていきますと・・・おお~、すばらしいじゃないですか、これは('-'*) どのくらいすばらしいかは、こちらのスクリーンショットをみていただければ一目瞭然でしょう。
分周比の兼ね合いで狙ったクロックへ落とし込むのが難しい(適当に設定すると起動直後にエラーをはき出してしまう)わけですが、整数倍で下げる分なら全く問題なく。285のクロックスペックは
2D:3D:MAX →
300/100/600:400/300/800:648/1242/1476 MHz (Core/Memory/Shader)
となっていますが、アイドル時でEvergreenに差をつけられたのはあちらが大胆な低クロック化を施してきたため(157/300MHz)、そして40nmプロセスが奏功して電力カットを実現できたものと思われます。
そこで私が施したのは「アイドル時のクロックを大幅にカットしてしまおう」というもので、コアクロックが150MHz、シェーダーは300MHz、メモリはそのままの100MHz。この値なら定格値の1/2きっかりとなるため、そのまま動作可能でした。
そして、「これだけ動作クロックが下がるのなら電圧も下げてしまえ!」ということで、こちらも大幅に下げて定格の1.05Vから0.80Vと、実に2割以上削減させています。電圧がこれだけ落ちると消費電力も下がるため(P=V^2/R)、総じてアイドル電力のカットが見込めます。
また、今回のカード2枚はGTX285の中でも後期のBIOSを積んでいることだけあって、チップに余力があるのか、定格クロックを定格電圧の1.15Vから1.07Vまで引き下げて、安定動作させられるところまで確認できました。もちろん、私の個体の場合、ですが。
元々はとあるところで 紹介します と書いておいて全然作る暇がなくて@@ 今更ながらに作ってみますけど、これなら余計にGTX480/470から遠のいてしまいます。このオリジナルBIOSならアイドル時30W程度、フル稼働時で160W以内で収められるバランスになっています。それも、ファン回転数はかなり抑えられた状態で、ですね。
今回あげた2枚のカードはいずれもGALAXY社のオリジナルファンを積んでおり、それをNVIDIA標準のファンと同じBIOSで動かすものですから、そのままではうるさいのなんの・・・。8cm角ファンを2300rpmなどで回そうものなら騒音にしかなりません。
フル稼働時ならまだしも、アイドル時からこれだけのパワーで回しても無意味です・・・。うるさいだけでなく、熱をまき散らしかねないですしね。ですので、無駄を絞って静かに冷やそうというのが本来の趣旨です。
NVIDIAのBIOSエディターである「NiBiTor」はシンプルにできており、ファンの回転数だけでなく電圧の調整も割と楽に行えることから、スクリーンショットを充実させてみました。ここであれこれ記載しなくても、画面を見ながら設定は簡単にできることでしょう。
一時期のエディター(Ver5.5)は作者にチップ(1ドル)をクレジットでPaypalしないと入手できなかったりですとか(アヤしい日本語ですね@@)、ファンが正しく動かない細かなバグが残ったりですとか、紹介できる内容ではないかな・・・と思っていましたら、最新版の5.6が完全フリーで公開され、バグもつぶされていましたので、この時期での紹介となります。
前置き長くなりましたが、この記事で伝えたいことは以下2点です。
・GeForceのファン回転数を、BIOSレベルから設定したい
・クロック周波数/電圧をチューニングしたい
いずれも効果は大きいものですが、最悪の場合はビデオカードを昇天させかねない内容です。この作業を行って損害が出たとしても、私は一切責任を負えませんので自己責任での実践をお願いします。
では、以下に手順を記しますね。とはいえ、RADEONのに比べたらかなり楽です。3ステップで構成されます。
1.必要なソフトを入手する(NiBiTor、nvFlash)
2.オリジナルBIOSをバックアップし、カスタムしたBIOSを作成する
3.カスタムBIOSをビデオカードに書き込む
今回も、私のサンプルromをおいておきます。極端な話、これをお手持ちの285に導入すれば・・・うまいこといけば、いいことになるんですけどね。一応下記分をしっかり把握してからということで。わからないまま安易に導入することは危険な行為ですので、お忘れのないように。
らべお手製 カスタマイズ済み オリジナルGTX 285 BIOS(GALAXY社向け)
∮ ∮ ∮
1.ソフトの入手は、こちらにてできますよ。BIOSをエディットするエディター「NiBiTor(NVIDIA BIOS Editor)」、そしてそのBIOSを書き込むための「nvFlash」。そちらのページからダウンロードしてくださいね。記載時点での最新バージョンはNiBiTorが5.6、nvFlashが5.88です。
さすがに、ビデオカードのBIOS書き換えをされるくらいですから、ダウンロードくらいは問題ないですよね('-')/
2.そして、ここが要になりますけど・・・まずはあらかじめビデオカードに格納されているオリジナルBIOSをバックアップしましょう。おなじみのGPU-Zから保存する方法です。GPU-Zのダウンロードはこちらからどうぞ。
まずはこちらを参考に、BIOSを保存しましょう。こちらがオリジナルとなるので、必ずバックアップをどこかにとっておきましょう。そうしないと、万が一元に戻す時にオリジナルがないと大変なことになりかねないからです。(一応techpowerupさんのBIOS Correctionで探すことはできますが・・・)
そうして、保存した後はいよいよ自分でBIOSをエディットしていきます。こちらを参考にしてみてくださいね。
ファンの回転数だけを調整する場合は、手順の「4~9」が該当します。Fanspeed ICと呼ばれるボタンの中にそれは隠されており、「min Duty cycle:」(最小回転数)のパラメータが該当します。初期値は40%ですが、NVIDIA純正ファンならこれで相応の静けさになりますけど・・・
今回のGALAXYさんのではうるさいだけです@@ ので、ここを1200rpmとなる17%まで絞り込みます。冷却に不安な場合はお好みで。20%で1400rpmくらいです。若干音が聞こえる程度ですので、そちらでも問題はないかと。他の値はいろいろ細かい挙動を調節できますけど、初期値が優秀なのでそのままで問題ありません。
自作をされている方ならご存じでしょうが、8cm角ファンは1200rpm未満であればほぼ無音のレベルです。1400あたりから少し耳につき、1600以上で認知できるレベルとなります(個人差はありますけどね)。
なのでファン回転数をこれだけ絞る以上、できる限り発熱を抑えたい・・・ということで、それ以降の手順で電圧を調整したり(12以降ですね)、最初の部分でクロックを書き換えたり(2のクロック値です)しているわけです。電圧だけは別のエディターから編集するようになっているというわけです。
そして、Voltage Table Editor(12~17)で注目するのは、Entry 1: ・ Entry :2 のパラメータ。これは1がアイドル時、2が3D動作時の電圧となっています。ここをテーブルエディターでいじってしまうわけですね。
サンプルはアイドルは下限となる0.8V、フルロード時で1.07Vにしています。定格がそれぞれ1.05V/1.15Vですので、特にアイドル時が大幅に引き下げられているの、おわかりいただけるかと。
もちろんフルロード時でも0.08Vあまり引き下げられているため、消費電力の低減に貢献しています。平均で30W程度はカットできています。つまるところ、RADEONでいうなれば5850と同等レベルまで抑えることに成功しているパラメータなのです(アイドル30W、フルロード160W)。それを285でできるのですからうれしい限りですよね。480/470では味わえない快適さです(取り扱いの点という意味で)。
ちなみに手順11のは、起動時に一瞬現れるVGA BIOSの情報部分を「表示しない」ようにチェックを外すというものです。不要な方はしておくといいかも。その分M/B BIOSへのアクセスが早くなります。
補足ですが、一番最初のスクリーンショットである動作周波数のところですが、私の場合はそちらも思い切って、2D/3D/Extraの3テーブルではなく、2D/Extraの2つに割り切っています。
なぜなら中負荷程度の3Dモードは、ほとんどそのモードになる前に負荷を検知してExtra(フルロード)となるため。そしてVoltage Table EditorでEntryを追加するとうまく追従してくれないような振る舞いを見せたため、2値で割り切って指定できるようにと配慮したためです。
そのため「アイドルか、フルか」という実に明快なパラメーターセッティングとなっています。これくらい明快だと取り扱いもしやすいですよね。
RADEONの記事でも検索語句に「Powerplayを無効化にしたい」あるいは「動作クロックを固定にしたい」で、たくさん調べられているみたいですからね。ちなみにRADEONで完全に動作周波数を固定にしたい場合は、全部のクロックボックスに同じ値を入れるだけです(笑)。こちらも同じですけどね。
以上で編集を終えてオリジナルBIOSを作成したら、後は書き込み作業を残すのみです。
3.いよいよオリジナルのBIOSを書き込む時です。MS-DOSでの起動を行って、コマンドプロンプトが現れたら、nvflashのファイルが置かれているディレクトリにて、以下のコマンドを打ち込むだけです。
nvflash -4 -5 -6 ファイル名.rom
 こちらの写真の場合では「NVF」フォルダを作成し、そこにnvflashを解凍したもの一式と、custom.rom を保存して、それを書き込むという手順を踏まえています。「cd NVF」はおわかりかと思いますけど、カレントディレクトリをルートからNVFへ切り替える(Change Directory)意味ですので。写真の問いかけのところまできましたら「y」キーを押すだけ。緊張の一瞬です・・・。
こちらの写真の場合では「NVF」フォルダを作成し、そこにnvflashを解凍したもの一式と、custom.rom を保存して、それを書き込むという手順を踏まえています。「cd NVF」はおわかりかと思いますけど、カレントディレクトリをルートからNVFへ切り替える(Change Directory)意味ですので。写真の問いかけのところまできましたら「y」キーを押すだけ。緊張の一瞬です・・・。
時間にして40秒程度ですが、無事に書き込みが終わった後は再起動をかけ、ファンが静かになったことを確認できれば終了です。お疲れさまでした('-'*)
∮ ∮ ∮
後書きみたいなもの
私の考え方は「オーバークロックは10%程度しか引き上げられないのに発熱・消費電力は2~3割増しになって取り扱いがしにくくなるくらいだったら、逆に定格動作を軸とした場合、どれだけマージンを削って動作電圧/アイドルクロックを引き下げ、エコなVGAを作り上げられるか」・・・ここにつきます。
なぜなら、アーキテクチャが変われば大幅なパフォーマンスアップも見込めるものの、よほど気に入ったゲームで、至高のパフォーマンスを追求でもしない限り、オーバークロックはあまり意味がないと思うからです。普段はアイドルが多いわけですしね。それなら日常使う部分を手入れした方が、より現実的なカードになるのでは・・・という発想です。
RADEONの時にも指摘したわけですが、アイドル時はどれだけクロックが高くても意味をなしえないように感じます。NVIDIAさんの300/100/600でもまだオーバースペック、無駄があると判断したので、ここまでカットしたわけなのです。おかげさまで、わずか1200rpmでも40度少々という、納得できる値に収められました。とても14億トランジスタのビッグチップが出すような値じゃないあたりが、「OC以外の自作」らしくて楽しいんじゃないかな?というわけです。
一応この温度、Antec SONATA Eliteっていう窒息ケースで出している温度なのですよ。コンパクトなATXケースですが、このケースでがんばるために、低電圧動作を考えたわけです。一応OC側に振った場合は702/1300/1504あたりまでできちゃうんですけどね。10%くらい性能は上がります。
Fermiはどちらかというとコンピューティング世代のGPUといった位置づけになっていて、ゲームが追いついていない現状では主役不在なのかもしれませんね。来年以降あたりならおもしろくなりそうですけど、今のところは静観でいいとは思います。さすがにここまでエコな285が作れたら、消費電力を倍加させてまでして480を使いたいとは・・・思わないですからね。改良されるといわれるGTX 485に期待したいものです。
・・・どこかこういったコンセプトのVGA作ってくれないですかねえ(汗笑)。調べ上げるのに丸1日はかかっちゃうんですよね・・・。
(GTX485はどうやらフルスペックのFermiになるみたいですね。これなら第2世代まで見送った方がいいのかも>消費電力などより増えそうな感じのため)
[ ビデオカード ]
投稿者 :lavendy | 2010年06月14日 15:33
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://lavendy.net/mt/mt-tb.cgi/212
コメント
有用な記事、ありがとうございます。
GALAXY GF PGTX285/1024D3/GE
BIOS Version: 62.00.77.00.01
ファンがうるさくて悩んでましたが、
おかげさまで静かになりました!!
「らべお手製 BIOSをエディットしよう」のスクリーンショット2ですが、
100/150/100 はクロックレートの変更効きませんでした。
150/300/100 ではないでしょうか?
投稿者 :なかもり | 2010年07月03日
お世話になります。なんと、このページに初のコメントが・・・;_; ある意味奇跡でしょう(汗笑)。
あうう・・・すみません@@ まさにご指摘の通りです・・・。お恥ずかしい限りです。文中の記載の仕方のまま操作をしているのがばればれですね(汗)。正しいものに差し替えておきました。ご不便をおかけさせてしまい、申し訳ありません。
おっしゃるとおりです。コア・シェーダーが300/600MHzですので、その半分となる150/300MHzが正解なのです。そしてメモリは両方変わらずの100MHz(DDRレートでは200MHz)。
ご利用のカードによりきき具合がどの程度変わるかまではわからないですけど、電圧やクロックはおまけみたいなものです。極論、元々のクロックは抑えられ気味のため、リーク電流でロスすると大差ないのでしょうしね。やかましすぎるファンを黙らせることが一番の目的です('-'*)
(ここには記載していませんが、GALAXYさんの275カードも同じ要領でチューニングできるのですよ。以前はそちらで確認しましたので。こちらもうるさかったです@@)
いずれにしましても「1でも変えられる要素があれば操作をし、微細な積み重なりを続けて大きな効果を得るコト」が、私の考え方ですので。無駄と思ってもチャレンジはします(^^;
静音化成功、おめでとうございました♪
投稿者 :らべ | 2010年07月03日
すばらしい情報ありがとうございます。
半年ほど前に中古のGALAXYのGTX285を購入し使っていたのですがコイル鳴き+ファンノイズがひどくどうにかならないものかと調べていたらこのページを見つけました。
クロックはそのままで電圧を1.1V/1Vにしてみたところコイル鳴きがうそのようにならなくなりました。
しかし調子に乗ってページに書いてある設定にしたところキュリキュリと音が・・・エコグラボにできなくて残念です。
ファンは10%台は怖いので20%でアイドル時大体51℃です(室温28℃~30℃
投稿者 :Anonymous | 2011年06月27日
にはは。お役に立てたようで何よりです('-'*)
なるほどなのです。中古で285はお買い得のような気はしますよね。DirectX 9でよければ十分な性能を今でも発揮はできますし。ただ、リファレンスボードのBIOSに8cmファンを取り付けてあるものですからうるさいことこの上なし・・・!なのでした □_ヾ( ̄∀ ̄*)
いえいえ、あまりやり過ぎても個体差レベルの違いや、元々それだけの駆動を見越した設計になっていないでしょうから、相応に低下できればしてやったり、なのではないでしょうか。
今度IntelさんもTDP枠をシフトするという発想に、ようやくたどり着いたみたいですからね。私はどちらかというとオーバークロックの上昇系よりは、電圧下げや低クロック化、言うなれば静音系を突き詰めるとTDP枠を下にスライドさせる・・・という視点が出てくるのではないかなって。
今はGTX570に移行しちゃっているのですけど、こちらもうまく設定できましたので、近いうち紹介しておきますね。
投稿者 :らべ | 2011年06月29日
Radeon HD 4870のところに投稿したかったのですが、出来なくなっているようですので、こちらにアップさせて頂きます。
REBの使い方をこれほど分かりやすくご説明され、大変尊敬しております。ご本でもお出しになっては如何でしょうか。
ところで参考にアップされたROMとオリジナルのHISのROMでは、ファンコントロールの最下欄に、幾分か数値を書き込まれていらっしゃいました。具体的には以下のパラメーターです。
Hysteresis(%)
Tmin hysteresis(℃)
Spin up cycle(%)
Spin up time(起動時間?)
PWM ramp on(on/off)
PWM ramp(%)
辞書等で調べましたが、単語自体はパソコン用語ではないので、話が広すぎて理解できませんでした。
先生は、どのような法則でファンの最下位欄を埋められたのでしょう。
正直、夜も眠れませんw
宜しければ、ご解説をお願い致します。ホントに・・・
投稿者 :KUMA | 2012年01月26日